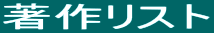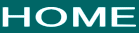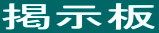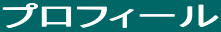月刊エッセイ 9/14/2002
■ 盗作? 、それともオリジナル?
あれあれ、まだやってたのか、と思いました。今月7日の新聞に、作曲家の小林亜星氏と服部克久氏の間で争われていた著作権訴訟の高裁判決が出て、一審とは反対に亜星さんの勝訴、「著作権侵害」での損害賠償が認められ、服部氏に約940 万円の支払い命令が出たと書いてありました。
この争いは、一審の際に週刊誌やテレビのワイドショーなどでさんざん取り上げられましたから、ご存じの方も多いでしょうが、おさらいをしておきましょう。服部克久氏が1992年に作った「記念樹」という曲が、小林亜星氏が66年に作曲したCMソング「どこまでも行こう」に酷似しているとの理由で、亜星氏が東京地裁に提訴したのです。そして、一審では「二つの曲は同一とはいえない」との判決が下り、亜星氏の敗訴。しかし、東京高裁での二審では、正反対の判決が出て、服部氏の敗訴。負けた服部氏のほうは、最高裁に上訴して、最後まで争うようです。お二人とも、元気なことですね。
両者の言い分のどちらが正しいのかは、音楽的才能がまったくない私( なにしろ「猫ふんじゃった」をピアノで弾くことも、「荒城の月」をハーモニカで吹くこともできないんですよ) には、まったく見当もつきません。しかし、著作権侵害とか盗作とかいう話題がマスコミを賑わすと、創作を生業としている人間としては、どうしても気になってしまうのです。
読者の方々は、プロ作家なら古今東西の小説を読み、最近話題の本もくまなく目を通しているとお思いかもしれません。しかし、内実は違います。一部の「本大好き」作家を除けば、プロになるほど小説を読まなくなるものです。なにしろ、新作を書くための資料を読み、取材で人にあったり、現地に飛んだり、そして本番である執筆に多大な時間を費やすのですから、ああ、それから私の場合など「家庭内ワークシェアリング」で家事の半分を引き受けているし、猫の相手もしなければならないので、他人が書いた小説を読む時間がそう簡単にはひねり出せないのです。
いや、精力的に他人の小説を読んだとしても、その量は知れています。今の日本では、毎年数千冊の小説が新刊書として市場に流れています。さらにかつて出版された本も合わせると、いったいどのくらいの小説がこの世には存在しているのでしょう。
自分が内容を知らない本がこれほどあれば、自著と似たようなものがすでに書かれているのではないかと、作家は悩むのです。いや、書く前、書いている最中に、似たようなモチーフの小説があることに気づいた時のほうが、悩みは大きいんですね。ある作家が「執筆に手間取っている間、海外ミステリーで○○の新作を読み、似たような構成になっているのを知って悩んだ。しかし、基本的には別なものだと判断して書き継いだ」といったような内容のあとがきを書いているのを読んだ記憶があります(
逢坂剛さんの「百舌の叫ぶ夜」だったと思うけど、記憶違いだったら、逢坂さん、ごめんなさい)
。
しかし、実際には、モチーフや構成が同じだったり、トリックが似ているくらいでは、マイナス点は大きくなりません。たとえば、今期の直木賞受賞作である乙川優三郎さんの「生きる」についても、「基本モチーフがあまりに森鴎外の『阿部一族』そのままだ」と書いている書評もあります。直木賞といえば、以前、阿刀田高さんが受賞した「ナポレオン狂」もロアルド・ダールの短編の中に似たような構成の作品があったように思います。しかし、両者ともめでたく賞を受けているのですから、同一性などどうでもよくなるほどに、内容そのものが評価されたんでしょうね。
でもねえ、現実に「似てるよ」と言われると、いい気持はしないんです。とりわけ、ミステリーを書いている作家の場合、トリックがいっしょだと指摘されることがある。たとえば、青酸カリを入れた水を凍らせてロックアイスにし、水割りのグラスに入れ、氷が溶けたのち人が死ぬというトリックは、今まで幾度も使われているんだそうです。おそらく、そのトリックを使った作家は、自分が最初だと思って書いたんだろうけど……。
私の場合を例にあげてみましょう。ネタバレになるやもしれませんが、だいぶ前の作品なのでかまわないでしょう。10年以上も前に「桜島1000キロ、殺人空路」というノベルズを書いています。そこでは、プッシュホンと電卓の数字配列の違いを利用したトリックが使われています。自信満々のトリックだったのですが、刊行後すぐに、ある編集者から、
「どこかで読んだ気がしますねえ。誰の小説だったかは憶えてないけど」
と言われて、にわかに不安になりました。こういう場合は、大量に本を読んでいるミステリー評論家に訊いてみるのがいちばんです。さっそく、山前譲氏に電話したところ、「少し待ってください」のあと、すぐに電話がかかってきました。さすがはミステリー評論家ですねえ。
「日下圭介さんの作品に似たものがあります」
とのご報告。「似てはいるが、ポイントとなる部分が違っているから、本岡さんのは別物だと思いますよ」という慰めの言葉を受けましたが、完全オリジナルだと思っていた私は意気消沈してしまいました。
この話には、後日談があるんですよ。それから5 年ほどたったある日、友人から電話があり、
「息子が読んでいる漫画に、本岡さんのトリックがそっくりそのまま使われている。これは、ぜったいに盗作ですよ」
さっそく書店に行って、その漫画雑誌を読んでみると、たしかに私が「桜島1000キロ殺人空路」で使ったトリックが、そのまま使われている。その雑誌を発行している出版社には知り合いの編集者もいるので、抗議しようかと思いましたが、考えた末、止めておくことにしました。
なぜなら、漫画の作者が私の作品を盗んだ可能性(まあ、こっちの線が強いんだろうけどね)もあるが、一方では、まったくの偶然によって同一のトリックが生まれた可能性も否定できないのです。
アインシュタインの相対性理論みたいなとんでもないものならともかく、だいたいが人間の考えることなど、そう大きくは違ってこないんです。私が考えついたトリックなら、他の人が考えついたって不思議じゃない。
俳句雑誌の編集者から聞いた話ですが、昭和天皇が病気で重態になった時、こんな俳句が数多く寄せられたそうです。
「○○○○○ 記帳の列に 秋の雨」
つまり、最初の五文字だけが違ってあとは同じという投句が、編集部にドドッと来たというのです。「粛々と 記帳の列に 秋の雨」「言葉なく 記帳の列に 秋の雨」(私は俳句の才能もないみたいだ。上手いのが浮かばない。あーあ、恥ずかしい)なんてのが、いっぱい来たということでしょうね。
昭和天皇の病気快癒を祈って、皇居前には記帳する者が列を作っている。そこに秋の雨が降っている。そんな情景を前にして、多くの人が似たような句を作ったというわけです。
そんなわけで、短い創作になればなるほど、同一作が出現する可能性も高くなるみたいです。歌会始の一般応募作で別の人が以前、発表した歌が選ばれた、短編の詰め将棋で同一作が見つかったなどということが、時々、話題になり、「これは盗作ではないか」と糾弾されたりもするようですが、私は偶然の一致の可能性もかなり高いのではないかと考えているんです。
人間の能力なんて、大天才を除けば、どれもチョボチョボ。同じような作品ができてしまったって、それは仕方のないことだ、と言い放ったとしても、やはり「盗作じゃないの?」という疑惑を向けられるのは、できれば避けたい。そこで、とくに短編を書いたりする時は、
(こんなの、誰でも浮かぶよな……)
と思われるようなアイデアは、面白いとは思っても、捨てたりすることがあります。
「幸運の女神は後ろ髪がない。前髪をつかめ」という言葉はご存じですよね。幸運はあとから追っかけても、つかむことができないから、早めにがっちり手を打っておけという意味だと思います。そのことを考えながら、うとうと居眠りをするうち、夢の中でかなりブスな幸運の女神に出会ったのです。目覚めて思いました。幸運の女神というのは美人じゃないから、前髪がつかめないんだ、と。
(よし、これを短編小説にしよう……)
考えていくと、アイデアはどんどん広がるではありませんか。だけど、少し冷静になってみると、美人じゃないから幸運の女神の前髪をつかめなかったなんて、誰でも考えつきますよね(それにアホみたいなアイデアでもあるし)。で、このアイデアは捨てることにしました。
幸か不幸か、作家の世界では、アイデアが似ているからといって、裁判に訴えられることはないようです。それは、もしかすると自分も似たような作品を書いているかもしれないという思いが、誰にもあるからではないでしょうか。
そういった意味も含めて、服部氏と亜星氏の問題を考えてみると、もし私が小林亜星氏だったら、裁判に訴えたりはしなかったでしょうね。もしかすると、自分も似たような曲を作っているのではと考えてしまうからです。とくに音楽の世界だったら、いつかどこかで耳にした曲が頭の中に染み込んでいて、自分のオリジナルだと錯覚してしまうことだってあるはずです。亜星氏は、
(おやおや、服部君の新曲は俺の「どこまでも行こう」にそっくりじゃないか。しかし、仕上がりは俺のほうが断然、上だな……)
と余裕を見せることはできなかったのでしょうか。
今回は、作家というのは、創作そのもの以外でも悩んだりするということを、ちょっと書いてみました。この商売も、いろいろ大変なんですよ、ほんと。